前回は、四代藩主鑑任治世の事績の一つ、平野山炭抗についてみてきました。
そこで今回は、三代鑑虎から五代貞俶まで最盛期を迎えた有明海干拓についてみてみましょう。
有明海の干拓
田中氏の治世下では、有明海の大規模な干拓事業が次々と行われたのは前にみたところです。
立花氏もこれを引き継いで、次々と有明海を干拓していったのです。

田中氏の干拓事業
ここで田中氏時代の干拓をおさらいしておきましょう。
田中吉政は三瀦郡の古賀村・浜武村や山門郡の有明海沿岸を干拓して数ヶ村を開くとともに、大川から柳川・大和・三池郡渡瀬までの有明海沿岸32㎞におよぶ慶長本土居(慶長土居)の築堤工事をおこないました。
次の忠政の代にも干拓事業は続けられて、慶長15年(1610)開拓村道海島、元和2年(1616)大野島村、翌元和3年(1617)浮島村と干拓地を次々と開いています。
用水確保への争い
じつは干拓事業は有明海の干潟を埋め立てればできるという簡単なものではありません。
堀割を巡らし盛土することで、土地をかさ上げして乾燥化させることはできるものの、今度は用水が不足する問題が起こるのです。
筑後平野を貫流する矢部川は、上流から下流にかけて久留米藩と柳川藩の藩境となったことから、水利をめぐる両藩の激しい争いの場となりました。
上流に久留米藩が花巡堰を設けて回水路を引くと、柳川藩はすぐ下流に三ケ名堰と回水路を築造して対抗し、より多くの流水を自藩側に取り込むために、下流側に黒木・込野・惣河内・唐ノ瀬・花宗といったように、両藩の堰と回水路が交互に築造されたのです。
昭和22年撮影空中写真(USA-M106-13〔部分〕)-2.jpg)
久留米藩は筑後川からの取水が可能であったのに対して、柳川藩は矢部川からしか取水できませんでした。
ですから、柳川藩にとって久留米藩との矢部川水利をめぐる争いは、絶対に負けられないものだったのです。
とはいえ、両藩は大きな衝突に発展しないよう暗黙のルールを守り、その中でそれぞれが工夫するにとどめていました。
干拓地の拡大
有明海の干拓事業は、前にみたように田中氏の時代に慶長本土居あるいは本土居と呼ばれる大規模な堤防が築造されて以降本格化しました
この本土居は、大川から柳川・大和・三池郡渡瀬までの有明海沿岸32㎞におよぶものだったのです。
田中氏断絶後に復帰した立花家も干拓には積極的で、本土居の外側に汐土居とよばれる堤防を築いて干潟の干拓を進めました。
延宝元年(1673)には、この汐土居の総延長が85㎞にも及んだといいます。
初期の干拓事例として知られるのが、大川市の紅粉屋(べにや)開です。
紅粉屋は、朱印船貿易や藩の貨幣方として活躍した豪商で、当主紅粉屋(後藤)成保がその財力を使って開発を行いました。
また、延宝5年(1677)以降は藩の事業として干拓が進められ、なかでもみやま市の黒崎開は200町歩にもおよぶ最大級のものです。
-2.jpg)
画面中央に水路に囲まれた逆T字形の部分が黒崎開です。 】
次回にみる田尻総馬の活躍もあって、柳川藩の干拓事業は江戸中期の元禄から延享にかけて最盛期を迎えます。
ちなみに、干拓地は明治初年で2,540町歩に達し、これは藩領のおよそ4分の1となる広さでした。
干拓地の種類
柳川藩の「開地(ひらきち)」と呼ばれた干拓地は、開発主体によって区別することができます。
藩営をはじめ、町人請負や百姓請負のほか、「御手元開」という藩主個人や、「給人開」という家老をはじめとする家臣による開発が多いという特徴がみられました。
収穫の取り分
また、干拓前の干潟に葭などを植えて利益を得ていたものを野主(のぬし)、干拓の開発権を獲得して開発資金を提供したものを地頭(じとう)、労働力を提供して実際の開発にあたったものを鍬先(くわさき)と呼んでいます。
野主と地頭は干拓地から余米とよぶ小作料を徴収する権利を持ち、鍬先にはその土地を実際に耕作する権利、小作権を持っていました。
また、干拓地は夫役が免除され、年貢も最初の10年間免除されたのちに、5~10年かけて段階的に引き上げられることになっていたのです。
いっぽうで、収穫の分割割合はというと、柳川市の七ツ家開における弘化2年(1845)分を例にとると、年貢2:鍬先4:地頭3:野主0.5:諸経費0.5となっています。
ここまで柳川藩の有明海干拓についてみてきました。
干拓事業の最盛期を現出した田尻総馬とは、どのような人物だったのでしょうか。
次回は田尻総馬についてみてみましょう。





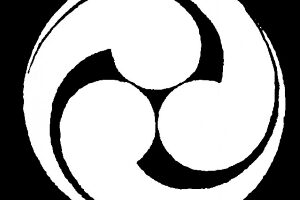
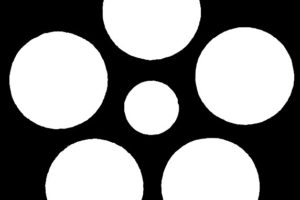
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
コメントを残す