前回は第二次長州征伐の直前までの状況をみてきました。
今回は、第二次長州征伐で最大の激戦となった芸州口の戦いのはじまりをみてみましょう。
作戦準備
幕府軍は、大島口・石州口・小倉口と芸州口から長州藩へ攻め込む作戦をたてます。
これに加えて萩口から薩摩軍が攻め込む計画でしたが、薩摩藩の出兵拒否により萩口への攻撃は取りやめとなりました。
ようやく慶応2年(1866)5月28日には老中本荘伯耆守宗秀が先鋒副総督として広島に入り、6月2日には小笠原長行が小倉開善寺の本営入り、さらに6月5日には先鋒総督に任ぜられた和歌山藩主徳川茂承が広島国泰寺の本営に入りました。
諸藩の兵も続々と集結し、いよいよ第二次長州征伐が幕を開けたのです。
-2.jpg)
四口の戦闘規模
ちなみに、四つの口の戦争規模を長州藩側の配備兵力でみると、大島口・石州口・小倉口はそれぞれおよそ1,000人規模であるのに対して、芸州口には倍の2,000人規模を配しています。
これは、幕府側が広島に征長先鋒総督府を設置したうえに、幕府陸軍や海軍および和歌山藩などの西洋式精鋭部隊を配置したことから、芸州口を大手口とみていたことに対応しているといってよいでしょう。
こうして芸州口において四つの口の中でも最大規模の激戦が繰り広げられることとなったのです。
開戦
ついに6月7日、幕府軍艦の大島砲撃をもって戦端が開かれます。
このとき紀州軍は、保守的な国柄を反映して今回の出兵では和流の陣立てで出陣していました。
まず和歌山藩軍が主力となった石州口をみてみましょう。
石州口には一之先に福山藩、二之見は浜田藩と津和野藩、応援は鳥取藩と松江藩、人数差出は先鋒総督の和歌山藩でした。
この大軍勢を、茂承の名代として和歌山藩付家老安藤直裕が指揮を執ったのです。
ただし、石州口における幕府軍の一部は西洋式武器を持つものの、ほとんどが古式ゆかしい士卒制の軍勢でした。
これを参謀・大村益次郎が実質指揮を執る長州軍が襲い掛かります。
.jpg)
6月16日に長州軍が増田に攻め込んで石州口でも開戦すると、征長軍は西洋式戦術を駆使する様式軍からなる長州軍に壊滅させられて敗走し、早くも7月18日には浜田城を自ら焼くまでに追い込まれたのでした。
そして、大島口での戦いも征長軍が6月20日に大島から逃げ出して戦闘は終結していたのです。
芸州口開戦
いっぽう、芸州口では、6月14日に先鋒を務める高田藩榊原家と彦根・与板藩井伊家の軍が国堺の小瀬川渡河をこころみて開戦します。
榊原家と井伊家は徳川四天王と称された家柄でしたが、両家ともに戦国時代以来の伝統的な陣容、槍隊を中心とした編成でした。
.jpg)
.jpg)
これに対する長州軍は、遊撃隊、維新団、衝撃隊、第一~四大隊、岩国兵で編成された西洋式軍隊でした。
そして、長州軍は散兵戦術を駆使して征長軍に襲いかかったのです。
旧式装備の幕府軍は総崩れとなって敗走、長州軍も驚くほどの長州軍大勝利となったのです。
名高き井伊家の「赤備え」も、ここではまったくの時代遅れで、目立つ赤色は恰好の射撃の的になってしまいました。
.jpg)
.jpg)
水野軍の軍制
長きにわたって徳川軍先鋒を務めてきた井伊と榊原両家の軍勢の大敗によって幕府の伝統的権威に傷がついたのはもちろん、征長軍の士気も低下にみまわれます。
このひどい状況で、いよいよ水野忠幹に出撃の命が下されました。
ここで忠幹が率いた軍について、改めてみておきましょう。
さきほど石州口の安藤軍でみたように、紀州軍は今回の出兵で和流の陣立てで出陣していました。
しかし忠幹は洋学も収める開明的な人物でしたので、独自の判断で「仕様のないので己れも旗を立て火縄筒を持つて来て居るが、到底役に立たぬから、内密にミニーを600挺持つてきた」といいます。
こうして独断で二、三中隊の歩兵とホーウィッスル砲2門を引率してきていたのです。
忠幹の率いる和歌山藩兵は江戸詰の藩士でしたので、赤坂藩邸の蘭学所で洋式調練を行っており、部隊はミニエー銃を装備していました。
忠幹直属の新宮兵はもちろんミニエー銃を装備したフランス式洋兵ですし、幕府歩兵と砲兵はもちろんフランス式。
つまり忠幹の率いる軍勢は、完全な西洋式近代軍だったのです。
こうして緒戦で大敗を喫した征長軍で、いよいよ水野忠幹率いる新宮・和歌山藩軍に出撃の命が下りました。
はたして忠幹は破竹の勢いで進撃する長州軍にどう挑むのでしょうか。
次回は、忠幹率いる新宮・和歌山藩軍と長州藩軍が激突した最初の戦闘、6月19日大野村戦争をみてみましょう。
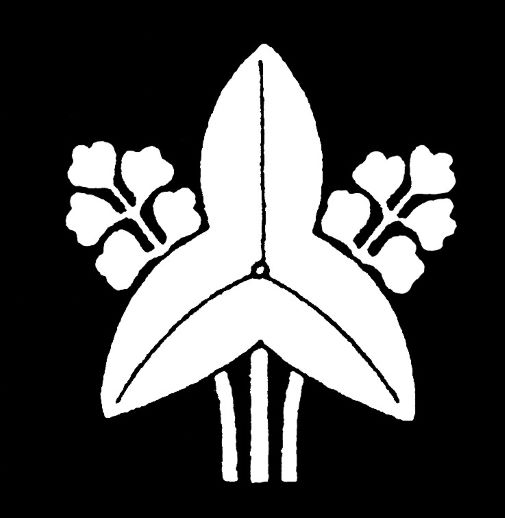

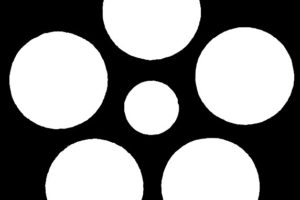





国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
コメントを残す