前回は、キリシタンたちが起こした島原の乱についてみてきました。
その後、キリスト教の広まりを恐れたこともあって、幕府は対外交易の場を長崎に限定し、出島を築いてオランダ商館を移すことで長崎奉行の監督下に置くこととしました。
こうなると、これまで南蛮貿易でつながっていたポルトガルとの関係はどうなったのでしょうか。
そこで今回は、正保4年(1647)のポルトガル船来航を中心に、鎖国への道のりをみていきましょう。
長崎警固
島原の乱でキリシタンに対する警戒を強めた幕府は、寛永16年(1639)7月にポルトガル船の来航を禁止します。
これに対して、寛永17年(1640)には通称継続を求めてポルトガルの使節が来航しました。
ところが、幕府は前年に宣告したとおり、下級船員はマカオに送還し、大使のゴンサロ・モンテイロ・デ・カルバーリョ以下61人を斬首したうえで、乗船を焼き沈めたのです。
ここまですると、当然ポルトガル側からの報復が予想されます。
そこで幕府は、寛永18年(1641)2月に福岡藩に長崎警固を命じ、翌年には佐賀藩がこれに代わると、以降は両藩が隔年で長崎を警固する体制が出来上がったのです。
そして一丁有事の際には、柳川藩をはじめ九州北部の大名たちが、当番の藩を救援することと定めました。
.jpg)
ポルトガル船来航
そしてついに正保4年(1647)6月、ポルトガル船二艘が長崎に入港します。
危惧されていたポルトガルの報復かと、長崎では緊張が高まりました。
そこで柳川藩主忠茂は、家老十時三弥を代将として士卒3,700余人を33艘に分乗させて長崎警固に出陣させます。
こうして、柳川藩はじめ九州諸藩から集められた兵は5万に達し、その威力を以てポルトガル船を追い返すことに成功したのです。
ポルトガルの思惑
いっぽう、ポルトガルからみれば、寛永17年(1640)の日本側の処置が予想をはるかに超える厳しさであったことから、関係者はかなりの動揺をきたしました。
じつは当時、オランダが台湾を拠点に東アジアでの貿易を活発化させたことでポルトガルは大きな打撃を受けて、本拠地マカオの繫栄にも陰りが見えていたのです。
このような状況でしたので、正保の使節も日本への報復などではなく、あくまでも交易再開を求める使節だったといいます。
しかし、幕府の強硬姿勢をみたポルトガルは、日本との交易をあきらめざるをえなかったのです。
こうしてポルトガルとの関係を絶った幕府は、対外交易の窓口を長崎に限定するとともに、貿易相手国をオランダと中国に制限する鎖国体制が確立しました。
国立国会図書館デジタルコレクション-2.jpg)
ちなみに、日本とポルトガルの交易が再開されるのは、日本が開国したのちに、日葡和親条約と日葡通商条約が結んだ万延元年(1860)で、215年後のこととなるのです。
今回まで柳川藩二代藩主立花忠茂の治世をみてきました。
そこで次回は三代鑑虎の時代をみてみましょう。
《今回の記事は、『福岡県史』『旧柳川藩誌』『福岡県の歴史』『三百藩藩主人名事典』『江戸時代全大名家事典』『国史大辞典』にもとづいて執筆しました。》

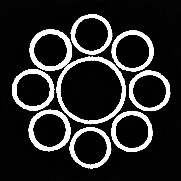
国立国会図書館デジタルコレクション補正-300x200.jpg)


-3.jpg)


国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
コメントを残す