前回まで見てきたように、明治時代の中頃まで橋の名前さえなかった鞍掛橋が、市電が通るようになって一躍表舞台に立ち、広く世に知られるようになりました。

そんな中、東京の街を、大正12年(1923)に関東大震災が襲います。
下町の多くが劫火にのまれて壊滅的被害を受け、鞍掛橋周辺も一面が焼け野原となる甚大な被害を受けました。
写真は橋近くの「浜町河岸」(『日本橋消防署百年史 明治14年-昭和56年』日本橋消防署、1981)で、地震火災のすさまじさがうかがえます。
鞍掛橋自体の損傷度合いは分かりませんが、かなり損傷が激しかったようで、復興事業で架け替えが決まります。
新しくなった橋の様子を写真付きで『帝都復興史 附・横浜復興記念史、第2巻』で詳しく掲載していますので、これを見てみましょう。
」『帝都復興史・附横浜復興記念史-第2巻』復興調査協会編(興文堂書院、昭和5年)国立国会図書館デジタルコレクション補正.jpg)
「鞍掛橋 浜町川に架けし鈑桁橋にて工費僅か四萬六千余円」と、タイトルは なによりも安くできた点を強調しているのが目を引きます。
橋が架かる場所は「(東京駅北口からのびる)幹線第十一号路線が、浜町川を横断する所に架設された橋梁」で、工期が「工事に着手したのは大正十五年六月にして、竣工は昭和二年八月」、費用は「総工費は四万六千五百七十三円であった」と記しています。
続いて、橋の構造は「橋の形式は鈑桁橋」、規模は「有効幅員は七米(二十七米の誤り?)、長さは十三米〇一五である。又有効面積は三百五十一平方米にして、桁下の空間限界は通常潮時に於て幅が八米二〇で高さは二米五〇」と、浜町川を通る舟を意識したのか桁下の大きさにも触れています。
幅が市電の幹線が通るには狭すぎるのが気になりますが、『中央区史 上巻』では鞍掛橋の規模を「長さ13,015m、幅27,838m」としているので、数字が欠落しているようです。

画面中央が鞍掛橋。】
『帝都復興史』ではさらに続けて、「高欄は橋上が二十八米六五にて、橋袖は同じく三米一〇であって、橋上は鋳鉄を橋袖は切石を用ひ」たと記しています。
写真に残る橋の姿を見ても、たしかに鋳鉄製の高欄が見えますが、写真で一番目立つ大きな四本の灯篭型親柱については触れていません。
さらに、「橋台の構造は基礎はコンクリートにして、躯体には割栗コンクリート工を施し、その表面は間知石とし隅は切石を以つて仕上げられたもの」と、橋が景観にも配慮した美しい橋であることが分かります。
こうして関東大震災の復興事業で美しい橋に生まれ変わった鞍掛橋ですが、その後わずか18年で、またもや大きな困難にぶつかります。

太平洋戦争末期の昭和20年(1945)3月、米軍による東京大空襲によって東京の下町一帯は再び壊滅的被害を受けてしまいます。
鞍掛橋周辺も例外ではなく、一面の焼け野原となりました。
「東京大空襲で焦土と化した東京」(『日本橋消防署百年史 明治14年-昭和56年』)を見ると、写真中央を横切るのが浜町川で木造建築物はすべて焼けていることから、画面の左枠外に当たる鞍掛橋付近も大きな被害を受けたものと推察できます。
そんな中でも この橋はなんとか空襲の劫火にも耐え抜いて、今度は戦災からの復興に役立つはずでした。
しかし、ここで新たな問題に直面します。というのも、戦災からの復興を邪魔する 空襲によって発生した膨大な灰燼の処分という難問が襲い掛かってきたのです。
昭和22年撮影の航空写真を見ると、画面中央の二車線と軌道のある橋が鞍掛橋ですが、浜町川沿いなどあちこちに灰燼の山があるのが分かります。

『中央区史 下巻』によると、「道路まで灰燼がうず高くつまれ、主要道路のこれをかたづけることが終戦後の急務であった。復興の第一歩として(昭和)二十年九月からまず灰燼処理事業からはじめることになった。(中略)(灰燼の多い千代田・港・台東)区の道路はどこも灰燼の山が築かれている有様であり、区内でも広いので有名な昭和通りも、中央部に灰燼の山をなす状態であった。これでは交通・衛生・公安上からもそのまゝにしておけない」という惨憺たる状態でした。
この問題を解決するために、「比較的流れがとまつたりして現在舟行に役立つていない川で、浄化の困難な実情にあるものを埋立て宅地とし、その土地を売つて事業費を取り返す」という一石二鳥の方策が採用され、浜町川の北半が対象となったのです。
こうして浜町川の埋めたてに先だって、昭和23年から鞍掛橋の撤去が始まります。
橋の撤去に続いて昭和24年には灰燼による浜町川の埋め立てが始まり、昭和25年に終了しました。

昭和38年撮影の空中写真を見ても、画面中央が鞍掛橋のあった場所ですが、橋の痕跡は見えません。
ついに、浜町川の延伸とともに誕生した鞍掛橋は、川と共に消滅したのです。
次回では、実際に鞍掛橋のあった場所を歩いてその痕跡を探してみましょう。
」『帝都復興史・附横浜復興記念史-第2巻』復興調査協会編(興文堂書院、昭和5年)国立国会図書館デジタルコレクション補正-718x524.jpg)



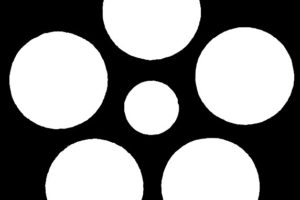




国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
国立国会図書館デジタルコレクション-アイコン用-300x200.jpg)
コメントを残す